はじめに
先日公開したイラスト『テラリウムからの脱出』のメイキングをまとめてみました。「水彩っぽい仕上げをしたい!」と考えている方は是非読んでみてください。
ラフと下描き


今回は描きたい物が決まっていたのでサクッと構図は決まりました。この時点では特に珍しいテクニックは使っていません。ビンを描くのに対称定規を使ったりはしましたが、テクニックと言うほどのものでは無いですね。
線画

もちろんラスターレイヤーに描いても良いのですが、普段マンガを描く時はベクターレイヤー上にペン入れをしているため、今回もベクターレイヤーを使用しました。使っているのはデフォルトの「リアル鉛筆」です。特に変更は加えていません。
ベースカラー

実のところ塗り分けなくても水彩風に仕上げることは可能なのですが、CGである以上「修正が楽なようにしておきたい」とも思うわけです。そのためにはそれぞれの範囲を簡単に選択出来た方が良い。…つまりこれは「色を決める」というよりも「範囲を分ける」作業なのです。
ここではパーツごとにレイヤーを分けるのではなく、ベースカラーは一枚にまとめています。その際、ほぼアンチエイリアスはかけず、領域拡縮でほんの少し外側に塗り足す程度にしています。
白地でクリッピング


水彩は紙の白を活かして塗っていきます。そのためには下手に色が塗られているとそれっぽくならないため、ベースカラーを白でクリッピングして、隠してしまいます。また、この時点でベースカラーを「参照レイヤー」に設定しておきます。
参照レイヤーを選択するツール


「隣接ピクセルをたどる」のチェックを外し「複数参照」の部分は参照レイヤー。そして、「編集レイヤーを参照しない」も選択しておきます。こうすることで参照レイヤー以外のレイヤーが選択されている場合、常に参照レイヤー上の色を選択することが可能になります。
パーツごとにレイヤーを分ける塗り方の方がポピュラーだと思いますが、その場合パーツが増えれば増えるほどレイヤーが増えまくって管理が大変になるので、僕はほとんどの場合ベースカラーは一枚にまとめ、参照レイヤーとして選択することで塗り分けることにしています。
基本色を塗る



ここでも基本はデフォルトのブラシを使います。コツとしては「エッジはある程度白く残す」ということでしょうか。もちろんそうでない箇所もありますが、特に髪の毛や肌などはエッジ付近を白く残した方がそこがハイライト的に明るくなるため、画面に埋もれません。
ちなみに今回は緑や青が多い画面のため、ポイントとなる部分にはそれと逆の暖色を使っています。
乗算でボケた影をのせる



透明水彩の特徴に「色を塗れば塗るほど濃くなる」という物があります。油絵などの場合は暗い色の上に明るい色を塗ると明るい色で暗い色を覆い隠せますが、水彩の場合はそうはいきません。
デジタルで水彩を再現する時も、その「濃くなる」特徴をシミュレートします。そのためにはレイヤーを「乗算」で重ねてあげるとうまくいきます。この段階での影はほとんどの場合同系色を塗っています。背景の緑の影には青、とかですね。
乗算でエッジの効いた影をのせる



アナログの水彩の場合、塗りのエッジがわずかに濃くなる場合があります。これを再現するのが「水彩境界」という機能です。うまく設定すると、非常にアナログっぽくなります。上記の拡大図の場合、後ろの森の影などが効果がわかりやすいかと思います。人物の場合、肌に落ちる髪の毛の影とかがわかりやすいですね。
スクリーンで空気感を加える



この辺はデジタルの利点をフル活用します。「スクリーン」という合成モードは「黒を透明として扱い、どんな色をのせても明るくなる」モードです。これを使って色の調整を行います。
背景を描く場合、奥に行けば行くほど薄く青くなる…と言う傾向があります。ここでもそれを再現するために、建物を中心に暗めの青いグレーをスクリーンで重ねます。こうすることで人物が目立つようになりました。
エッジがハッキリしている物とボケている物を分けてあるのは、その方が修正が楽だからです。
鮮やかなハイライト




レイヤーの合成モードを「加算(発光)」にして黄色寄りの茶色を塗ると、鮮やかなハイライトとして使えます。もちろんこれもアナログではあり得ない表現ですが、お手軽に綺麗になるのでよく使っています。
また、ハイライトとは逆方向の照り返し部分には、環境光を考えた色も塗っています。男の子の後ろにはガラスがあるためその色を反映させて青(水やガラスの色が青いというわけではなく、これは空の色を写しているからそう見える、という解釈です)。女の子は緑の中に座っているため、髪の毛などの下側に緑を足しています。
ガラスの反射を描く

アナログの透明水彩の場合、ほとんど白は使いません。ただ、今回のようにガラスの反射などを描く場合には使うこともあります。
「水彩っぽさを表現する場合、乗算が有効」と言いましたが、乗算レイヤー上で白を塗るとそれは透明として扱われてしまうため意味がありません。そのため、ここでは通常レイヤーに描いています。
テクスチャをのせる


乗せるレイヤーは絵によって変えるのですが、今回の場合三枚乗せています。左から順に「水彩」のテクスチャ。合成モードはオーバーレイです。オーバーレイは明るい部分はスクリーンとして、暗い部分は乗算として重なる合成モードです。真ん中が「紙の繊維」テクスチャ。これは「ソフトライト」で乗せました。ソフトライトは、オーバーレイのかかりが弱い版、くらいに考えておいてもらえれば問題ないと思います。右側は「アルシュ」。これは高級水彩紙のテクスチャです。以前買った紙をスキャンしてテクスチャ化した物で、結構気に入って使っています。

「アルシュ」のテクスチャのみレイヤープロパティ上で「質感合成」にチェックを入れています。オーバーレイで重ねると白い部分はそのまま白になりますが、質感合成の場合、わずかに紙のテクスチャが反映されます。ただ、そこまでテクスチャを主張させたくない時はオーバーレイで乗せてしまっても良いと思います。もちろん質感合成の「強さ」を下げても良いでしょう。
完成

また、もう少し詳しい水彩メイキングが書籍化されているため、気になった方は是非購入の検討をよろしくお願いいたします。
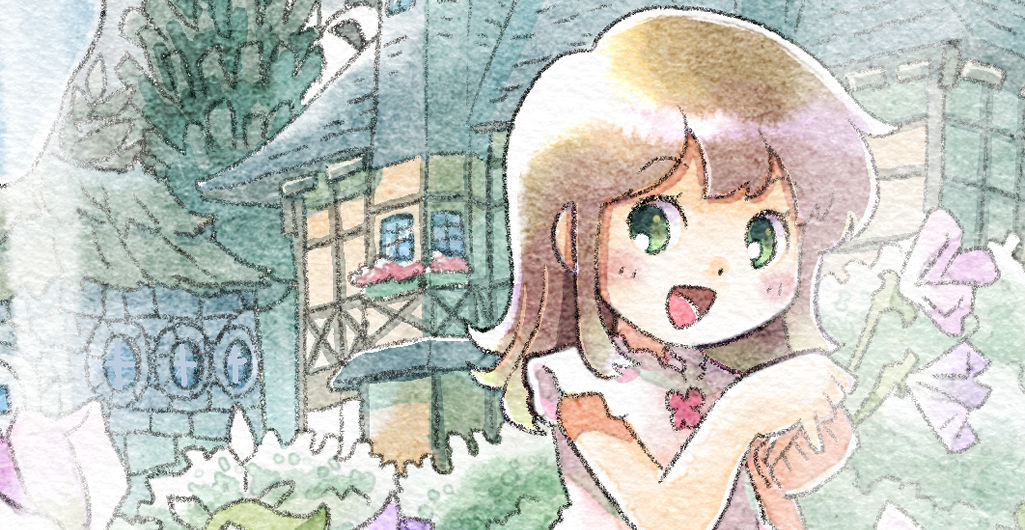
 CLIP STUDIO PAINTで描くマンガの描き方の教則本、【改訂版】!好評発売中です。
CLIP STUDIO PAINTで描くマンガの描き方の教則本、【改訂版】!好評発売中です。
















なんともありがたい記事です!!
逆にい、いいんですか!?と驚きです。
参考にさせていただきます。
本当におめでとうございます。
お体無理なく、活動頑張ってください。